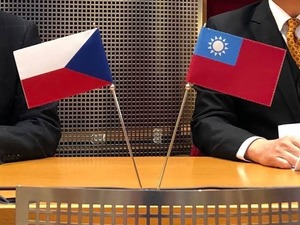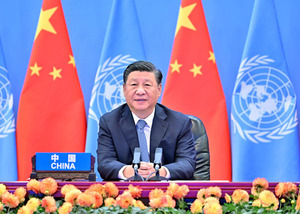赤の他人同士だったら、些細な問題で関係が急に悪くなることは少ないかもしれない。逆に兄弟関係だったなら、事態は俄かに複雑な状況になることがある。ちょっとした誤解から関係が急速に険悪化し、最悪の場合、兄弟関係が途絶えてしまう事態も予想される。

▲訪日したチェコのヤン・リパフスキー外相と会談する上川陽子外相(2024年2月29日、日本外務省公式サイトから)
チェコとスロバキアは冷戦時代は「チェコ共和国」と「スロバキア共和国」から成るチェコスロバキア連邦国家であり、東欧共産圏の一国だった。それがビロード革命と呼ばれる民主改革で共産政権が崩壊した。その後、1918年から両共和国で構成されていた連邦国家は1993年に平和裏に分かれた。両国はその後、欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、欧州の一員としてこれまでそれぞれの道を歩んできた。
興味深い点は、チェコ連邦の国民の多数は当時、連邦解体を希望していなかったという事実だ。チェコ側もスロバキア側でも連邦の解体に関する国民投票は実施されず、政府と議会での討議後、連邦解体が決定された。連邦解体の背景について、スロバキアのウラジミール・メチアル元首相は、「チェコ政府側は経済力の脆弱なスロバキアから離れたいという意向が強かった。連邦解体はチェコ側が久しく願ってきたプランに基づいて遂行されていった。スロバキア側はそれに抵抗する手段はなかった」と、オーストリア日刊紙プレッセとのインタビューの中で述懐している「『チェコ連邦』の解体が決まった日」2017年8月28日参考)。
その兄弟国だったチェコとスロバキア両国がここにきて険悪な関係となってきた。というより、ロシア軍のウクライナ侵攻後、EUのウクライナ支援に積極的に関わるチェコに対し、スロバキアはウクライナ支援に消極的で、ロシアのプーチン大統領の強権政治に傾斜してきたのだ。
その両国間の政府間協議がチェコ側の申し出で無期延期されたことから、両国間の間に亀裂が生じてきた。ペトル・フィアラ首相率いるチェコ政府は6日、親ロシア派のロベルト・フィコ首相率いるスロバキア政府との間で予定されていた慣例の政府協議を中止すると決定した。フィアラ首相は、「スロバキア政府の活動の一部には問題がある。通常の政府間会合を開催することは現時点では適切ではないということで一致した」というのだ。チェコ側はこの措置についてスロバキア側に既に通知済みだという。
チェコ側が反発している問題はスロバキア政府のウクライナ政策がロシアに融和的過ぎるという点だ。具体的には、スロバキアのジュラジ・ブラナール外相が今月2日、トルコのアンタリヤでロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談したことが報じられると、チェコ側はスロバキア政府の外交政策に危険を感じ出したわけだ。
チェコのペトル・パベル大統領は7日、ウクライナに対して数週間以内に80万発の砲弾を追加供給できると発表した。これはチェコ主導のプロジェクトであり、弾薬不足のウクライナを支援する狙いがある。チェコはウクライナ戦争勃発後、他のEU諸国と同様、対ロシア制裁を実施する一方、旧ワルシャワ条約機構時代の武器を提供してきた。同時に、ウクライナからの避難民を積極的に迎え入れてきた。
チェコのフィアラ首相は、「チェコ社会とスロバキア社会の間に緊密なつながりがあることを認識しているし、私たちは協力を継続し、両国関係とプロジェクトの発展に興味を持っている。しかし、いくつかの外交政策問題については大きな意見の相違があるという事実を隠すことができない」と説明し、今回の政府決定への理解を求めている。
一方、スロバキアのロバート・フィコ首相は6日、プラハからの発表に激怒し、「チェコとスロバキアの関係を危険にさらす決定だ。わが国はウクライナ戦争の平和的解決について語っているのに、チェコ政府は戦争の継続に関心がある。わが国のウクライナ政策には変更はない」と強調する一方、「わが国のチェコとの緊密な関係を危険にさらすようなことはしない」と述べ、両国関係の険悪化がエスカレートしないように注意を払っている。
EUのブリュッセルでは、スロバキアがハンガリーのオルバン首相の親ロシア政策に倣い、フィコ首相が第2のオルバンになるのではないかと懸念している。フィコ首相は昨年10月、ウクライナへの軍事支援をやめるという公約を掲げて4度目の政権復帰をした左派指導者だ。
チェコとスロバキア両民族は兄弟関係だったが、民族の気質は異なっている。1989年11月の民主化プロセス(ビロード革命)でもチェコでは民主化後初代大統領となったバーツラフ・ハベル(Vaclav Havel)氏ら知識人を中心とした政治運動が、スロバキアではキリスト信者たちの信教の自由運動がその民主化の核を形成していった。チェコ民族とスロバキア民族の気質の相違が民主化運動でも異なった展開となった(「『プラハの春』50周年を迎えて」2018年8月10日参考)。その違いがウクライナ問題でも表面化しているといえるかもしれない。物事を合理的に政治的に判断する傾向が強いチェコ民族と、情熱的、宗教的気質が強いスロバキア民族では、ウクライナ戦争に対する対応で相違が出てくるのはある意味で当然かもしれない。
https://wien2006.livedoor.blog/archives/52220971.html
ちなみに、今年11月の米大統領選でトランプ氏が再選された場合、米国ファーストを標榜するトランプ政権のウクライナ政策が激変するかもしれない。プーチン大統領のロシアとの関係でも変化が予想される。同じように、ハンガリー・ファースト、スロバキア・ファーストを標榜してきたオルバン首相やフィコ首相の対ウクライナ政策やロシアへの融和政策に変化や修正が出てくることが考えられる。

▲訪日したチェコのヤン・リパフスキー外相と会談する上川陽子外相(2024年2月29日、日本外務省公式サイトから)
チェコとスロバキアは冷戦時代は「チェコ共和国」と「スロバキア共和国」から成るチェコスロバキア連邦国家であり、東欧共産圏の一国だった。それがビロード革命と呼ばれる民主改革で共産政権が崩壊した。その後、1918年から両共和国で構成されていた連邦国家は1993年に平和裏に分かれた。両国はその後、欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、欧州の一員としてこれまでそれぞれの道を歩んできた。
興味深い点は、チェコ連邦の国民の多数は当時、連邦解体を希望していなかったという事実だ。チェコ側もスロバキア側でも連邦の解体に関する国民投票は実施されず、政府と議会での討議後、連邦解体が決定された。連邦解体の背景について、スロバキアのウラジミール・メチアル元首相は、「チェコ政府側は経済力の脆弱なスロバキアから離れたいという意向が強かった。連邦解体はチェコ側が久しく願ってきたプランに基づいて遂行されていった。スロバキア側はそれに抵抗する手段はなかった」と、オーストリア日刊紙プレッセとのインタビューの中で述懐している「『チェコ連邦』の解体が決まった日」2017年8月28日参考)。
その兄弟国だったチェコとスロバキア両国がここにきて険悪な関係となってきた。というより、ロシア軍のウクライナ侵攻後、EUのウクライナ支援に積極的に関わるチェコに対し、スロバキアはウクライナ支援に消極的で、ロシアのプーチン大統領の強権政治に傾斜してきたのだ。
その両国間の政府間協議がチェコ側の申し出で無期延期されたことから、両国間の間に亀裂が生じてきた。ペトル・フィアラ首相率いるチェコ政府は6日、親ロシア派のロベルト・フィコ首相率いるスロバキア政府との間で予定されていた慣例の政府協議を中止すると決定した。フィアラ首相は、「スロバキア政府の活動の一部には問題がある。通常の政府間会合を開催することは現時点では適切ではないということで一致した」というのだ。チェコ側はこの措置についてスロバキア側に既に通知済みだという。
チェコ側が反発している問題はスロバキア政府のウクライナ政策がロシアに融和的過ぎるという点だ。具体的には、スロバキアのジュラジ・ブラナール外相が今月2日、トルコのアンタリヤでロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談したことが報じられると、チェコ側はスロバキア政府の外交政策に危険を感じ出したわけだ。
チェコのペトル・パベル大統領は7日、ウクライナに対して数週間以内に80万発の砲弾を追加供給できると発表した。これはチェコ主導のプロジェクトであり、弾薬不足のウクライナを支援する狙いがある。チェコはウクライナ戦争勃発後、他のEU諸国と同様、対ロシア制裁を実施する一方、旧ワルシャワ条約機構時代の武器を提供してきた。同時に、ウクライナからの避難民を積極的に迎え入れてきた。
チェコのフィアラ首相は、「チェコ社会とスロバキア社会の間に緊密なつながりがあることを認識しているし、私たちは協力を継続し、両国関係とプロジェクトの発展に興味を持っている。しかし、いくつかの外交政策問題については大きな意見の相違があるという事実を隠すことができない」と説明し、今回の政府決定への理解を求めている。
一方、スロバキアのロバート・フィコ首相は6日、プラハからの発表に激怒し、「チェコとスロバキアの関係を危険にさらす決定だ。わが国はウクライナ戦争の平和的解決について語っているのに、チェコ政府は戦争の継続に関心がある。わが国のウクライナ政策には変更はない」と強調する一方、「わが国のチェコとの緊密な関係を危険にさらすようなことはしない」と述べ、両国関係の険悪化がエスカレートしないように注意を払っている。
EUのブリュッセルでは、スロバキアがハンガリーのオルバン首相の親ロシア政策に倣い、フィコ首相が第2のオルバンになるのではないかと懸念している。フィコ首相は昨年10月、ウクライナへの軍事支援をやめるという公約を掲げて4度目の政権復帰をした左派指導者だ。
チェコとスロバキア両民族は兄弟関係だったが、民族の気質は異なっている。1989年11月の民主化プロセス(ビロード革命)でもチェコでは民主化後初代大統領となったバーツラフ・ハベル(Vaclav Havel)氏ら知識人を中心とした政治運動が、スロバキアではキリスト信者たちの信教の自由運動がその民主化の核を形成していった。チェコ民族とスロバキア民族の気質の相違が民主化運動でも異なった展開となった(「『プラハの春』50周年を迎えて」2018年8月10日参考)。その違いがウクライナ問題でも表面化しているといえるかもしれない。物事を合理的に政治的に判断する傾向が強いチェコ民族と、情熱的、宗教的気質が強いスロバキア民族では、ウクライナ戦争に対する対応で相違が出てくるのはある意味で当然かもしれない。
https://wien2006.livedoor.blog/archives/52220971.html
ちなみに、今年11月の米大統領選でトランプ氏が再選された場合、米国ファーストを標榜するトランプ政権のウクライナ政策が激変するかもしれない。プーチン大統領のロシアとの関係でも変化が予想される。同じように、ハンガリー・ファースト、スロバキア・ファーストを標榜してきたオルバン首相やフィコ首相の対ウクライナ政策やロシアへの融和政策に変化や修正が出てくることが考えられる。