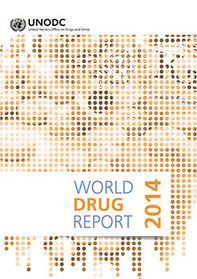世界が滅ぶとすれば、核兵器による戦争勃発、地球の温暖化が直ぐに思い浮かぶが、「最もリアルなシナリオは化学物質による地球汚染だ」という声が聞かれる。化学物質による地球環境の破壊、土壌の汚染、化学物質から生産された食料(食品添加物など)によるアレルギーの脅威、化学物質過敏症、化学物質から生産された合成麻薬類の拡大など、化学物質による脅威は今日、地球規模で悪影響を与えてきているというのだ。
例えば、ウィーンに本部を置く国連薬物犯罪事務所(UNODC)が26日公表した「2014年世界麻薬報告書」は化学物質から合成された麻薬類の拡大に警戒を与えている。特に、麻薬製造に利用される化学物質、前駆物質の管理の重要性を強調している。ちなみに、20世紀前半、化学物質を生産する国は欧米諸国に限られてきたが、2010年現在、化学物質の世界最大生産地はアジア諸国(全体の44%)に移動している。同時に、化学物質が合成麻薬の前駆物質として利用されるケースが急速に広がっている。アジア地域で合成麻薬が拡大してきたのは決して偶然のことではない。
国連は1988年、「麻薬および向精神薬の不正取引に関する国際条約」を最訳して、化学物質の管理に乗り出している。具体的には、国際薬物統制委員会(INCB)が前駆物質の管理を担当している。前駆物質には今年1月現在、エフェドリン、無水酢酸など23の化学物質がリストアップされているが、その数は年々増加傾向にある。
実例を挙げれば、北朝鮮が風邪薬製造に利用されるエフェドリンを独薬品会社に大量注文したことがある。コール独政権(当時)が「北朝鮮の国内需要量を上回るエフェドリンの注文は怪しい」として独企業に輸出禁止を要請したことがある。北はエフェドリンで大量の合成麻薬を製造する計画だったと見られている。
化学物質による土壌汚染問題では留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs)がある。ストックホルム条約は2001年5月に採択され、04年5月に発効した。POPsとは、毒性が強く、分解が困難で長期間、人体や環境に悪影響を与える化学物質だ。ダイオキシン類やDDTだ。DDTは有機塩素系の農薬でPOPsの規制対象物質だ。日本では1971年に使用が禁止されたが、同条約に加盟していない北朝鮮はDDTをまだ使用している(「北朝鮮のPOPs問題」2007年5月19日参考)。
POPsの怖さは、悪影響が一国だけに留まらず、地球全土に拡大することだ。平壌がDDTの使用を中止しなければ、土壌が汚染し、その影響は時間の経過と共に他国にも拡大する。簡単にいえば、北朝鮮のPOPsは偏西風やグラスホッパー現象などを通じて日本にも影響を与える。日本で久しく使用されていないPOPsが国内の土壌から検出されたということが度々起きる理由だ。その意味で、POPsは国際規制が不可欠となるわけだ。急速に経済発展する中国の環境汚染問題は最近、大きく報道され、その影響はアジア近隣諸国だけではなく、地球規模に及ぶと指摘され出した。大気汚染から水質汚染、土壌汚染まで、その汚染影響は計り知れない。
化学物質の生産は国家の経済発展を久しく支えてきたが、21世紀に入って地球を覆う有害化学物質が人類の健康を蝕む主要要因となってきた。そこでPOPs条約、「有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約」などの国際条約が採択され、国際的な化学物質管理戦略的アプローチ(SAICM)が2006年2月、国際化学物質管理会議で採択され、「2020年までにすべての化学物質を人の健康や環境への影響を最小化する方法で生産、利用する」ことを目指している。
例えば、ウィーンに本部を置く国連薬物犯罪事務所(UNODC)が26日公表した「2014年世界麻薬報告書」は化学物質から合成された麻薬類の拡大に警戒を与えている。特に、麻薬製造に利用される化学物質、前駆物質の管理の重要性を強調している。ちなみに、20世紀前半、化学物質を生産する国は欧米諸国に限られてきたが、2010年現在、化学物質の世界最大生産地はアジア諸国(全体の44%)に移動している。同時に、化学物質が合成麻薬の前駆物質として利用されるケースが急速に広がっている。アジア地域で合成麻薬が拡大してきたのは決して偶然のことではない。
国連は1988年、「麻薬および向精神薬の不正取引に関する国際条約」を最訳して、化学物質の管理に乗り出している。具体的には、国際薬物統制委員会(INCB)が前駆物質の管理を担当している。前駆物質には今年1月現在、エフェドリン、無水酢酸など23の化学物質がリストアップされているが、その数は年々増加傾向にある。
実例を挙げれば、北朝鮮が風邪薬製造に利用されるエフェドリンを独薬品会社に大量注文したことがある。コール独政権(当時)が「北朝鮮の国内需要量を上回るエフェドリンの注文は怪しい」として独企業に輸出禁止を要請したことがある。北はエフェドリンで大量の合成麻薬を製造する計画だったと見られている。
化学物質による土壌汚染問題では留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs)がある。ストックホルム条約は2001年5月に採択され、04年5月に発効した。POPsとは、毒性が強く、分解が困難で長期間、人体や環境に悪影響を与える化学物質だ。ダイオキシン類やDDTだ。DDTは有機塩素系の農薬でPOPsの規制対象物質だ。日本では1971年に使用が禁止されたが、同条約に加盟していない北朝鮮はDDTをまだ使用している(「北朝鮮のPOPs問題」2007年5月19日参考)。
POPsの怖さは、悪影響が一国だけに留まらず、地球全土に拡大することだ。平壌がDDTの使用を中止しなければ、土壌が汚染し、その影響は時間の経過と共に他国にも拡大する。簡単にいえば、北朝鮮のPOPsは偏西風やグラスホッパー現象などを通じて日本にも影響を与える。日本で久しく使用されていないPOPsが国内の土壌から検出されたということが度々起きる理由だ。その意味で、POPsは国際規制が不可欠となるわけだ。急速に経済発展する中国の環境汚染問題は最近、大きく報道され、その影響はアジア近隣諸国だけではなく、地球規模に及ぶと指摘され出した。大気汚染から水質汚染、土壌汚染まで、その汚染影響は計り知れない。
化学物質の生産は国家の経済発展を久しく支えてきたが、21世紀に入って地球を覆う有害化学物質が人類の健康を蝕む主要要因となってきた。そこでPOPs条約、「有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約」などの国際条約が採択され、国際的な化学物質管理戦略的アプローチ(SAICM)が2006年2月、国際化学物質管理会議で採択され、「2020年までにすべての化学物質を人の健康や環境への影響を最小化する方法で生産、利用する」ことを目指している。